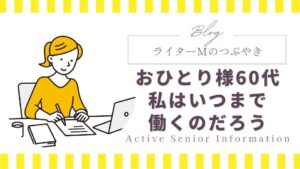友達と話してても、墓じまいした話はすごくみんな興味があるみたいです。
60代になってからというもの、人生のあれこれを「どう整理しておこうかな」と考える時間が増えました。
ひとり暮らしで息子はすでに30代。遠方に家族を持って暮らしている弟もいる。
これから先、私が70代、80代になったときに、身の回りや家のことをどう残していくか――
頭の片隅にずっと引っかかっていたのが両親はじめ「お墓」のことだった。
うちの実家のお墓は、今の住まいから車で1時間以上かかる山寄りの地域にある。
両親が眠る大事な場所だけれど、車がないと行けない立地。
私の家族以外はほとんどお参りに行かなくなっていた。弟も若い頃は顔を出していたが、今は自分の家庭を持ち、遠方に住んでからは、ほぼ来てない。
「70代になって運転できなくなったらどうしよう?」
「息子や弟の子どもたちに負担をかけるのでは?」
「でも墓じまい考えるのは両親や先祖の軽視になるかな?」
最初はなんとなく重いテーマで、口にするのもはばかられたが、そんな不安を抱えて、弟とはもう5年ほど前から「墓じまい」の話をしていたのです。
「実際にお墓いけないことが一番の親不孝であり、先祖不幸じゃない?」という弟の言葉は背中を押してくれました。
一番大きなきっかけは私の大病。
「もし今後もっと動けなくなったら?」と考えざるを得なかった。そこから本格的に動き出したのだ。
住職への相談と納骨堂への移転
お墓をどうするか。最近は「永代供養」や「共同納骨堂」という選択肢が増えていると耳にしていた。
けれど、実際にお世話になっているお寺に相談するとなると、少し勇気がいる。
寺院によっては墓じまいを歓迎しない場合もあると聞いていたからだ。
幸い、うちの住職は理解があり、「系列の納骨堂なら安心ですよ」と紹介してくださった。
しかも、その納骨堂は電車で行ける場所にあり、将来的にもお参りしやすい。
弟も私も「これなら続けられる」とほっと胸をなでおろした。
正直なところ、寺院や墓苑によっては「移転はできない」と断られることもあるらしい。そういう意味では、私たちは運がよかったのかもしれない。
手続きと移動の日のこと
墓じまいにはいろいろと手続きがある。
改葬許可証の申請や元のお寺からの承諾書、新しい寺院への受け入れ証明…。細かい書類を揃える作業は、想像以上にエネルギーがいる。
そして、いよいよ「お骨を移す日」。
骨壷を車に積んで、弟と二人で走らせたのだが――これがなんともシュールな光景だった。
助手席には骨壷、バックミラー越しに自分の顔と骨壷が並ぶ。
不謹慎かもしれないけれど、思わず「ドライブのお供みたいだね」と苦笑してしまった。弟も同じように苦笑いしていて、緊張が少しほぐれた。
気になる費用のこと
「墓じまいはお金がかかる」とよく聞く。
実際、最初に調べたときには300万円なんて数字が出てきて、「とてもじゃないけど無理だ」と一度は諦めかけた。
でも今回、同じ県内での移転だったこともあり、かかった費用は合計でおよそ80万円。
内訳は、元の墓地での石材撤去費用、寺院への謝礼、新しい納骨堂への支払い、そして石材店への依頼料など。もちろん決して安い金額ではないけれど、想定していたよりはずっと現実的だった。
「やればできるんだ」と思えたことは、気持ちの面でも大きな収穫だった。
墓じまいを終えて思うこと
こうして無事に両親を新しい納骨堂へと移すことができた。今は、電車で通える距離にお墓があることに、とても安心している。
お墓はご先祖さまと向き合う大切な場所。
でも同時に、残された家族の暮らしや負担の現実とも深く関わっている。今回の墓じまいで痛感したのは、「元気で動けるうちに決断しておくこと」の大切さだ。もし私がもっと年を取ってからこの問題に向き合っていたら、きっと弟や息子に大きな負担をかけていたと思う。
これから残っている課題は「実家じまい」だ。
こちらもお金がかかるし、決断には勇気がいる。でも、弟と私が元気なうちに片付けておけば、次の世代が困らなくて済むはずだ。
最後に
墓じまいを経験して思うのは、これは「寂しい終わり」ではなく「未来への整理」なのだということ。
過去をないがしろにするのではなく、これからを生きる人たちに迷惑をかけないための前向きな準備だと感じている。
ひとりで生きる私にとって、この選択は大きな安心をもたらしてくれた。まだまだ不安は尽きないけれど、「動けるうちにやっておこう」という気持ちがあれば、案外いろんなことが片付いていくのかもしれない。