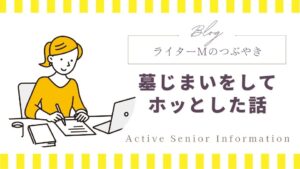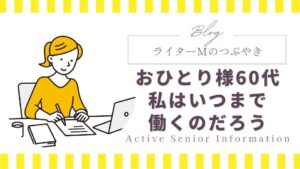両親は早くに亡くしましたが、叔父の介護の話を今日は。
ちょっと赤裸々なので、苦手な方がいましたら、すみません。
叔父の認知症が進んで
ここ数年、叔父の介護に携わるようになりました。
正直、日々いろんなことを悩ませられます。実家に住んでる分、距離があるので、月2日程度の訪問なのですが通院が多い時は週1日で訪問しています。
私の叔父はバツイチで独り身。長年企業で働いていましたが、退職と共に数年前から私の両親も住んでいた実家に一緒に暮らすようになりました。
私のイメージの叔父はアクティブで外出好き。母が生きていた頃は、遊びに行っても出掛けていないなんてしょっちゅうでした。大好きな雀荘があり、ボケ防止だと麻雀を楽しんでいました。
4年前に雀荘の階段から酔っ払って転倒し足を怪我したことから、自宅にいるようになり要介護1となりました。
基本は近くのコンビニへ買い物ができるので、夕飯だけお弁当の宅配を手配し、本人は家ではスポーツ新聞とビールがを片手に、のびのび過ごしていました。怪我から階段を登るのが慎重になり、雀荘へは行かなくなりました。
行動が範囲が狭まると同じくして、外出好きだった分近所付き合いがほぼないので、自宅に篭るようになりました。年々家が荒れてくので、実家によっては掃除をしたり、洗濯したりと補助的に叔父の世話をしていました。
しかし、急激に認知症が進んでしまい、今はレビー小体型認知症の症状が進んでいます。
おかしいと思ったきっかけ
おかしいと思ったのは、今までは「来てくれてありがとうね」と言ってた叔父が「俺のこと監視でもしているのか?」と言い出したり「2階に人がいるだろう」みたいなことを言い出したことです。
最初は、2階に上がり確認し「誰もいないよ〜」と伝えました。特にその時はニュースで高齢者宅への強盗事件の報道が多かったので、心配もあり、何かあればすぐに110番するように伝えました。
先日、財布が見つからなくなったときのこと。電話がかかってきて心配で出たら「Mがこの前来た時に、俺の財布持って帰っただろう!」と言うのです。もちろんそんなことはしてないので、伝えたのですが、後日警察に通報したみたいで、警察から電話かかってきた時は疑われてることに、すごく落ち込みました。
もちろん警察もちょっと言動がおかしいのをわかっていたそうで、あくまでも確認のためとは言っていましたが、正直、ショックは隠せませんでした。
先日は「通帳がなくなった」「印鑑がない」とのこと。持っていってないよと話したら、おかしいおかしいと言うので、叔父とタクシーで再発行の手続きをしました。
しかし、これが仇となり「俺の通帳はMに監視されている」「俺の印鑑を複製したに違いない」などありもしない妄想で、私を頼る割には、泥棒扱いもしてくるようになったのです。
ずっと世話をしてきたのに、なぜ盗人扱いされなきゃならないのか…。正直、その言葉に胸がえぐられる思いでした。



この時のショックはまだ強く、書いてて泣けてきました。
レビー小体型認知症に多い症状
ケアマネさんに相談し、本人が嫌がる中でしたが、健康診断と銘打って、病院に診断する中で、レビー小体型認知症との診断が下りました。
- 幻視(実際にはない人や虫、物が見える)
- もの盗られ妄想(財布・通帳などを盗まれたと信じ込む)
- 注意力や認知機能の波(今日はしっかり、翌日はぼんやり)
- パーキンソン症状(手足の震えや歩行の不安定さ)
- 眠っているときの大きな叫びや体動
こうした症状は「本人が嘘をついている」わけではなく、病気による脳の働きの変化から起きているものだそうです。
「正論」で返すと関係が崩れることも
最初のうちは「盗んでないよ」「忘れてるだけでしょ」と言ってしまいました。
でもそれは逆効果。叔父の目はますます疑いの色を強め、関係がぎくしゃくしていきました。
ケアマネさんに状況を話す中で、何度か泣きながら話すと、教えていただいたのは、
大事なのは「事実」ではなく、「叔父が今感じている不安」ってことだけはわかってください。
本人の中では「財布がない」どうしようという焦りとパニックから妄想に発展していると
とのことでした。
でも、泥棒扱いされていい気持ちになる人なんていないよという本音はありますが、その話を聞いた後に叔父の家に行った際にも今度は「鍵がない。M知らないか?またお前が持って帰ったのか?」と言われました。
「また」って言葉にカチンときてますが、ぐっと堪え「鍵がないの?」「大丈夫?困ったね、それは不安だね」と言ってみました。いつもなら泥棒扱いだけの叔父がその日は落ち着いて話すことができ「そうなんだね、一緒に探そう」と話して一緒に探しました。
変な引き出しに入っていたのですが、そこで「見つけた!」なんて言えば、また泥棒扱いされそうなので、「あっち側見てみた?」と誘導し、叔父自身に見つけてもらいました。
「あった!あった!」と嬉しそうですが、泥棒扱いしたことへの謝罪はないので、正直モヤモヤは残りました。
介護者だって疲れる
とはいえ、四六時中「寄り添いモード」でいるのは難しい。
こちらも人間だから、つらい言葉に心がすり減ってしまうことがあります。そんなときは、
- 他の家族に一時的に入ってもらう
- ケアマネージャーに相談してデイサービスを活用する
- 自分も趣味や友人との時間を持つ
そうやって介護者自身が距離を取り、心を守る工夫が大切だと感じています。



私は、ケアマネさんと連携とることで、訪問回数を減らしました。
月1でもモヤモヤはもちろんしますが、だいぶ楽になりました。
私自身の気持ち
「なぜ私ばかり」と思う夜もあります。けれど、叔父にとって一番近しい存在である私だからこそ、怒りや疑いの矛先が向いてしまうのかもしれません。
友人に話すと同じようなレビー小体型認知症で近所のおばあさんとトラブルやご両親とトラブルって話は思ったよりもありました。
みんな上手に上手に施設や介護サービスを使ったり、もう、世話しないと決めたりと色々悩みながら対処をしていました。
私自身も叔父に施設を勧めましたが、なかなか難しく、今は自宅で一人頑張ってもらっています。
それでも、「怖い」「不安」という叔父の心の叫びに気づけるのは、私しかいないのも現実。
私も疲れないようにうまくやろうと思っています。
最後に
介護はきれいごとばかりではありません。ときには心をえぐられるような言葉を受けることもあります。
でも、それは病気のせいであって、自分を否定しているわけではない――そう頭で理解しつつも、心がついていかないときもあります。
そんなときは、無理せず「距離をとる」「誰かに頼る」。
それが介護を長く続けるための、そして自分自身を守るための大事な選択肢なのだと思います。
同じように介護で悩んでいる方へ。
「頑張りすぎないで」と、自分自身にも言い聞かせながら、今日もまた叔父と向き合っています。